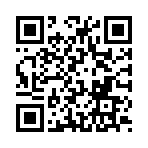「社会の木鐸」を標榜したラジオ日本の遠山景久
かつて遠山景久(とおやま かげひさ、1918年(大正7年) - 1999年(平成11年))というアール・エフ・ラジオ日本の社長、会長がいた。遠山は東京府東京市神田区神田(現:東京都千代田区神田)出身。「遠山の金さん」こと江戸化政の町奉行・遠山景元の末裔にあたる。幼少の頃、借財を抱えていた父と死別し、判事を務めていた長兄の下で日本統治時代の台湾・台北で育つ。
次兄・景弘は、東北帝国大学(現:東北大学)に在学中に左翼運動(共産主義運動)に共鳴しており、日本共産党中央再建準備委員会にも参加したが1937年2月に逮捕され獄死。旧制中学卒業後、封建的な三兄・武夫の許に預けられ、厳しい監督下で育つがのちに家出し、愚連隊に身を投じることになる。
1941年(昭和16年)応召。陸軍士官候補生を経て将校となり、従軍した。1945年(昭和20年)の敗戦後は、軍隊の資材を米軍に没収される前に確保して、それを元手として東京・銀座で運送会社を興して、一時・隆盛を極めた。1946年(昭和21年)1月、日比谷公園で開催された野坂参三の歓迎国民大会に参加して、復員軍人の一人としてアジ演説を行ったこともある。同時期、運送会社のあった銀座で飲食店を開業するが、GHQが飲食店事業の禁止令を発動したため、反発し全国の同業者に呼びかけて組織化し反対運動を展開するも頓挫。終戦からしばらくは左翼思想に共鳴しつつ、小規模な事業を展開するが、後に右翼・反共活動に転向するようになる。
出版社『論争社』を経営する傍らで政治評論家としての顔も併せ持つようになる。アール・エフ・ラジオ日本の前身であるラジオ関東の創設者であった河野一郎の遺族からの要請を受けて、『論争社』を経由して1967年(昭和42年)、ラジオ関東に入社。この時点で副社長を務めるようになる。
1970年代後半に入ると、テレビ・ラジオの各局はこぞって新聞社との資本提携を図るようになり、1974年(昭和49年)に東京放送(TBS)から撤退した読売新聞社も新たなラジオの提携先を模索するようになった。元々神奈川県のローカル放送局でしかなかったラジオ関東は、当然ながら神奈川県中心の地域しか放送対象としなかったが、1977年(昭和52年)読売新聞社側が巨人戦の単独独占中継権とネット局を含む自社の宣伝及びニュース放送を抱き合わせで契約したいと突如言いはじめ、これはNRNのキー局である文化放送・ニッポン放送(フジサンケイグループ)や、JRNのキー局で毎日新聞系のTBSラジオにはどうしても無理な注文で、結局独立独歩の路線であったラジオ関東がこの無茶な提案を敢えて呑んだ事で、読売新聞社と提携した。
これを皮切りに1981年(昭和56年)社名を「ラジオ関東」からアール・エフ・ラジオ日本と改名した(冒頭にアール・エフと付くのは、当時新社名に改名した際、ニッポン放送から名称使用差し止めの仮処分を申し立てられたことや、NHKの日本国外向け国際放送・NHKワールド・ラジオ日本と紛らわしくなるためである)。
社号を改名した直後から、所謂(いわゆる)『社会の木鐸(ぼくたく)』という宣言をし、左派系マスコミの糾弾キャンペーンを展開し始めた遠山は、ロックやアイドルタレントを番組から排除すると言いはじめ、反共・タカ派的な報道・論説番組を中心として(放送法は第1条第2項により放送局の不偏不党・自律を保障しているため、通常テレビ・ラジオは論説や社説を流さない。 各種の論評番組はその論説委員個人の意見である)、一日中、演歌やジャズを流す編成に変貌。同じタカ派のマスコミ経営者でありながら、人事に干渉するフジサンケイの鹿内に対して、編成・製作に干渉する遠山とまで言われた。
1987年(昭和62年)に社長を駒村秀雄に譲り遠山自身は会長に退くも、事実上社内に院政を敷いて影響力を行使した。1989年(平成元年)には、夜9時以降に残っていた若者向け番組は全てなくなった。1990年(平成2年)、「大人の放送局」を編成の基本方針とし、50歳以上の聴取者をメインターゲットとするようになる。
1991年(平成3年)には一度スポンサーと契約した声優のラジオ番組(「林原めぐみのHeartful Station」など)を突如放送しないなどといった行為まで発生し、その結果、聴取率は年を追うごとに低下し、アール・エフ・ラジオ日本の売上げは激減した。
その後も遠山の強引な経営は続き、アナウンサーをキーパンチャーに転属させ訴訟となったり、管理職の研修を自衛隊で行うなど、労使関係は険悪な状況となり退職者が相次ぎ(アナウンサーとして同局に在籍していた山本剛士のように、他局に移籍したケースもある)、最盛期には150名以上いた社員が30名ほどとなった。経営末期の1993年(平成5年)には打ち切られた番組が21本などと異常な状況となり、ワンマン体制に堪えられなくなった社員は、1993年(平成5年)12月21日、駒村社長以下取締役会全会一致で「公共の電波を預かる放送会社の代表としてはふさわしくない」として遠山を解任。後任の社長には読売新聞社・日本テレビ出身の外山四郎が就いた。1994年(平成6年)2月には、アール・エフ・ラジオ日本から「不当な事業で会社に与えた損害の返済」を要求され、遠山の自宅を差し押さえられた。これらの影響により、遠山一族所有のアール・エフ・ラジオ日本の株式を読売新聞の傘下にある日本テレビが買取り、残りの額を日本テレビ系列愛の小鳩事業団(現:日本テレビ小鳩文化事業団)に譲渡した。
なお、「社会の木鐸」終了後、編成方針については、当初は競合他局との差別化を図る意図から劇的な変化を避け、長年にわたりミッキー安川を複数番組で重用し、没後も実子のマット安川を起用している他、演歌番組も多く編成するなど、高齢者志向を続けていた。また、報道面では2009年(平成21年)11月に深夜放送「ラジオ時事対談」を開始する等、遠山時代の名残だけでなく、現在提携関係にある読売新聞・日本テレビの影響もあり保守的傾向となっている。2000年代以降には以前排除されたアイドル系タレントが参加する若者向けの番組が主に週末を中心に増えつつあり、イメージ払拭のキャッチフレーズに「こんな番組もやってます」として夜のアイドルパーソナリティの写真を中心に散りばめた広告戦略を打っている。さらに2015年春から深夜枠「ラジオ日本NEXT」を開始し、アイドル番組枠を大幅に増やした。一方2016年秋から諸事情で形式的にはDJを入れ番組と編成しているが実体としてはフィラーと言える枠も少しずつ現れている。
次兄・景弘は、東北帝国大学(現:東北大学)に在学中に左翼運動(共産主義運動)に共鳴しており、日本共産党中央再建準備委員会にも参加したが1937年2月に逮捕され獄死。旧制中学卒業後、封建的な三兄・武夫の許に預けられ、厳しい監督下で育つがのちに家出し、愚連隊に身を投じることになる。
1941年(昭和16年)応召。陸軍士官候補生を経て将校となり、従軍した。1945年(昭和20年)の敗戦後は、軍隊の資材を米軍に没収される前に確保して、それを元手として東京・銀座で運送会社を興して、一時・隆盛を極めた。1946年(昭和21年)1月、日比谷公園で開催された野坂参三の歓迎国民大会に参加して、復員軍人の一人としてアジ演説を行ったこともある。同時期、運送会社のあった銀座で飲食店を開業するが、GHQが飲食店事業の禁止令を発動したため、反発し全国の同業者に呼びかけて組織化し反対運動を展開するも頓挫。終戦からしばらくは左翼思想に共鳴しつつ、小規模な事業を展開するが、後に右翼・反共活動に転向するようになる。
出版社『論争社』を経営する傍らで政治評論家としての顔も併せ持つようになる。アール・エフ・ラジオ日本の前身であるラジオ関東の創設者であった河野一郎の遺族からの要請を受けて、『論争社』を経由して1967年(昭和42年)、ラジオ関東に入社。この時点で副社長を務めるようになる。
1970年代後半に入ると、テレビ・ラジオの各局はこぞって新聞社との資本提携を図るようになり、1974年(昭和49年)に東京放送(TBS)から撤退した読売新聞社も新たなラジオの提携先を模索するようになった。元々神奈川県のローカル放送局でしかなかったラジオ関東は、当然ながら神奈川県中心の地域しか放送対象としなかったが、1977年(昭和52年)読売新聞社側が巨人戦の単独独占中継権とネット局を含む自社の宣伝及びニュース放送を抱き合わせで契約したいと突如言いはじめ、これはNRNのキー局である文化放送・ニッポン放送(フジサンケイグループ)や、JRNのキー局で毎日新聞系のTBSラジオにはどうしても無理な注文で、結局独立独歩の路線であったラジオ関東がこの無茶な提案を敢えて呑んだ事で、読売新聞社と提携した。
これを皮切りに1981年(昭和56年)社名を「ラジオ関東」からアール・エフ・ラジオ日本と改名した(冒頭にアール・エフと付くのは、当時新社名に改名した際、ニッポン放送から名称使用差し止めの仮処分を申し立てられたことや、NHKの日本国外向け国際放送・NHKワールド・ラジオ日本と紛らわしくなるためである)。
社号を改名した直後から、所謂(いわゆる)『社会の木鐸(ぼくたく)』という宣言をし、左派系マスコミの糾弾キャンペーンを展開し始めた遠山は、ロックやアイドルタレントを番組から排除すると言いはじめ、反共・タカ派的な報道・論説番組を中心として(放送法は第1条第2項により放送局の不偏不党・自律を保障しているため、通常テレビ・ラジオは論説や社説を流さない。 各種の論評番組はその論説委員個人の意見である)、一日中、演歌やジャズを流す編成に変貌。同じタカ派のマスコミ経営者でありながら、人事に干渉するフジサンケイの鹿内に対して、編成・製作に干渉する遠山とまで言われた。
1987年(昭和62年)に社長を駒村秀雄に譲り遠山自身は会長に退くも、事実上社内に院政を敷いて影響力を行使した。1989年(平成元年)には、夜9時以降に残っていた若者向け番組は全てなくなった。1990年(平成2年)、「大人の放送局」を編成の基本方針とし、50歳以上の聴取者をメインターゲットとするようになる。
1991年(平成3年)には一度スポンサーと契約した声優のラジオ番組(「林原めぐみのHeartful Station」など)を突如放送しないなどといった行為まで発生し、その結果、聴取率は年を追うごとに低下し、アール・エフ・ラジオ日本の売上げは激減した。
その後も遠山の強引な経営は続き、アナウンサーをキーパンチャーに転属させ訴訟となったり、管理職の研修を自衛隊で行うなど、労使関係は険悪な状況となり退職者が相次ぎ(アナウンサーとして同局に在籍していた山本剛士のように、他局に移籍したケースもある)、最盛期には150名以上いた社員が30名ほどとなった。経営末期の1993年(平成5年)には打ち切られた番組が21本などと異常な状況となり、ワンマン体制に堪えられなくなった社員は、1993年(平成5年)12月21日、駒村社長以下取締役会全会一致で「公共の電波を預かる放送会社の代表としてはふさわしくない」として遠山を解任。後任の社長には読売新聞社・日本テレビ出身の外山四郎が就いた。1994年(平成6年)2月には、アール・エフ・ラジオ日本から「不当な事業で会社に与えた損害の返済」を要求され、遠山の自宅を差し押さえられた。これらの影響により、遠山一族所有のアール・エフ・ラジオ日本の株式を読売新聞の傘下にある日本テレビが買取り、残りの額を日本テレビ系列愛の小鳩事業団(現:日本テレビ小鳩文化事業団)に譲渡した。
なお、「社会の木鐸」終了後、編成方針については、当初は競合他局との差別化を図る意図から劇的な変化を避け、長年にわたりミッキー安川を複数番組で重用し、没後も実子のマット安川を起用している他、演歌番組も多く編成するなど、高齢者志向を続けていた。また、報道面では2009年(平成21年)11月に深夜放送「ラジオ時事対談」を開始する等、遠山時代の名残だけでなく、現在提携関係にある読売新聞・日本テレビの影響もあり保守的傾向となっている。2000年代以降には以前排除されたアイドル系タレントが参加する若者向けの番組が主に週末を中心に増えつつあり、イメージ払拭のキャッチフレーズに「こんな番組もやってます」として夜のアイドルパーソナリティの写真を中心に散りばめた広告戦略を打っている。さらに2015年春から深夜枠「ラジオ日本NEXT」を開始し、アイドル番組枠を大幅に増やした。一方2016年秋から諸事情で形式的にはDJを入れ番組と編成しているが実体としてはフィラーと言える枠も少しずつ現れている。
Posted by
うさぎいぬ
at
18:00
│Comments(
0
)