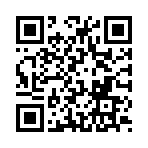今日の歳時記…7月12日
[今日が誕生日]
●ジョサイア・ウェッジウッド(英陶芸家《ウェッジウッド社の創設者》・1730年生)
●アメデオ・モディリアニ(画家・彫刻家・1884年生)
●芥川也寸志(作曲家・指揮者・文豪芥川龍之介の子・1925年生)
●京唄子(漫才師・司会者《唄子・啓助のおもろい夫婦》・1927年生)
●中村玉緒(女優・1939年生)
●四谷シモン(人形作家・1944年生)
●真弓明信(元プロ野球・阪神監督・1953年生)
●北別府学(元プロ野球・1957年生)
●森永卓郎(経済アナリスト・1957年生)
●片平なぎさ(女優《2時間ドラマの女王》・1959年生)
●梅垣義明《通称:梅ちゃん》(俳優《WAHAHA本舗》・声優・1959年生)
●渡辺美里(ミュージシャン・1966年生)
●イ・ビョンホン(韓国俳優・1970年生)
●クリスティー・ヤマグチ(フィギュアスケート《アルベールビル五輪金メダル》・1971年生)
●クリスティアン・ビエリ(伊サッカー・1973年生)
●石井義人(プロ野球・1978年生)
●アントニオ・カッサーノ(伊サッカー・1982年生)
[今日が命日]
●角倉了以(豪商・1614年没・61歳)
●山下清(画家・1971年没・49歳)
●臼井吉見(作家・1987年没・82歳)
●中村光夫(文芸評論家・1988年没・77歳)
●安川加壽子(ピアニスト・1996年没・74歳)
[今日の歴史]
●1192年
源頼朝が征夷大将軍となる。鎌倉幕府をつくる。
●1925年(大正14年)
東京放送局(JOAK・後のNHK)がラジオの本放送を始める。
●1959年(昭和34年)
田中聡子選手が200m背泳で2分37秒1の世界新記録を出す。戦後初の日本人女性世界新。
●1963年(昭和38年)
政府が生存者叙勲の復活を決定。
●1971年(昭和46年)
"放浪の画家""はだかの大将"と呼ばれた山下清画伯がこの日都内で死去。東京・浅草に生まれ38歳で銀座の画廊で初個展を開催。代表作は、桜島、草津温泉など。
●1972年(昭和47年)
「ハイセイコー」が大井競馬場でデビュー。デビュー後はぶっちぎりの6連勝。翌年には中央入り。東京優駿でタケホープに敗れるまで10戦10勝と不敗神話を作った。
●1993年(平成 5年)
北海道南西沖でマグニチュード7.8の地震が起き、奥尻島を津波が直撃。高さ30メートルの津波が奥尻島を直撃し、奥尻島青苗地区は壊滅状態となり、230人に上る死者・行方不明者を出す大惨事となった。
●1997年(平成 9年)
宮崎駿監督によるスタジオジブリの長編アニメーション映画「もののけ姫」が封切。興行収入192億円、観客動員数1420万人を記録。当時の邦画歴代興行収入第1位となる。
[今日の暦と記念日]
◆日本標準時制定記念日
1886年(明治19年)の7月12日、東経135度を日本の標準時とし、1888年(明治21年)1月1日よりこれを実施するとの勅令が公布されたことに由来。これにより、兵庫県明石市の正午が全国どこでも同じ正午となった。なお、明石市相生町にある子午線標識は、1928年(昭和 3年)に昭和天皇の即位を記念して建造されたもの。
◆ローリング・ストーンズ記念日
1962年(昭和37年)のこの日、ローリング・ストーンズが初めてロンドンのクラブに出演したことを記念。
◆人間ドックの日
1954年(昭和29年)東京の国立第一東京病院で「人間ドック」が始められたことを記念し。
◆洋食器の日
新潟県燕市にある日本金属洋食器工業組合が、代表的な洋食器のナイフ(712)の語呂合わせからこの日を「洋食器の日」と制定。
[この頃、こんな季節]
●鬼灯(ほおずき)
◆夏になると真っ赤な実をつける「ほおずき」。赤い実の中身を抜いて口に入れ、鳴らしたこともあるだろう。
◆ほおづきは、6月頃に淡い黄白色の花をつけ、やがてガクが大きくなり、ちょうど袋をかぶせたように実を包み込んでしまう。ほおずきが店に出てくるのはお盆前くらいから。
◆ほおずきといえば東京・浅草、浅草寺のほおずき市が有名だが、福岡市西区の愛宕神社でもこの頃「ほおずき祭り」が行われる。境内は2000鉢程のほおずきで一杯になり即売会も行われる。
◆ほおずきの見分け方。茎がしっかりとしていて、実の付きがよいものを選ぼう。
◆ほおずきの育て方。日当たりのよい場所で育てよう。表面の土は、常時湿っている程度がいい。
●ジョサイア・ウェッジウッド(英陶芸家《ウェッジウッド社の創設者》・1730年生)
●アメデオ・モディリアニ(画家・彫刻家・1884年生)
●芥川也寸志(作曲家・指揮者・文豪芥川龍之介の子・1925年生)
●京唄子(漫才師・司会者《唄子・啓助のおもろい夫婦》・1927年生)
●中村玉緒(女優・1939年生)
●四谷シモン(人形作家・1944年生)
●真弓明信(元プロ野球・阪神監督・1953年生)
●北別府学(元プロ野球・1957年生)
●森永卓郎(経済アナリスト・1957年生)
●片平なぎさ(女優《2時間ドラマの女王》・1959年生)
●梅垣義明《通称:梅ちゃん》(俳優《WAHAHA本舗》・声優・1959年生)
●渡辺美里(ミュージシャン・1966年生)
●イ・ビョンホン(韓国俳優・1970年生)
●クリスティー・ヤマグチ(フィギュアスケート《アルベールビル五輪金メダル》・1971年生)
●クリスティアン・ビエリ(伊サッカー・1973年生)
●石井義人(プロ野球・1978年生)
●アントニオ・カッサーノ(伊サッカー・1982年生)
[今日が命日]
●角倉了以(豪商・1614年没・61歳)
●山下清(画家・1971年没・49歳)
●臼井吉見(作家・1987年没・82歳)
●中村光夫(文芸評論家・1988年没・77歳)
●安川加壽子(ピアニスト・1996年没・74歳)
[今日の歴史]
●1192年
源頼朝が征夷大将軍となる。鎌倉幕府をつくる。
●1925年(大正14年)
東京放送局(JOAK・後のNHK)がラジオの本放送を始める。
●1959年(昭和34年)
田中聡子選手が200m背泳で2分37秒1の世界新記録を出す。戦後初の日本人女性世界新。
●1963年(昭和38年)
政府が生存者叙勲の復活を決定。
●1971年(昭和46年)
"放浪の画家""はだかの大将"と呼ばれた山下清画伯がこの日都内で死去。東京・浅草に生まれ38歳で銀座の画廊で初個展を開催。代表作は、桜島、草津温泉など。
●1972年(昭和47年)
「ハイセイコー」が大井競馬場でデビュー。デビュー後はぶっちぎりの6連勝。翌年には中央入り。東京優駿でタケホープに敗れるまで10戦10勝と不敗神話を作った。
●1993年(平成 5年)
北海道南西沖でマグニチュード7.8の地震が起き、奥尻島を津波が直撃。高さ30メートルの津波が奥尻島を直撃し、奥尻島青苗地区は壊滅状態となり、230人に上る死者・行方不明者を出す大惨事となった。
●1997年(平成 9年)
宮崎駿監督によるスタジオジブリの長編アニメーション映画「もののけ姫」が封切。興行収入192億円、観客動員数1420万人を記録。当時の邦画歴代興行収入第1位となる。
[今日の暦と記念日]
◆日本標準時制定記念日
1886年(明治19年)の7月12日、東経135度を日本の標準時とし、1888年(明治21年)1月1日よりこれを実施するとの勅令が公布されたことに由来。これにより、兵庫県明石市の正午が全国どこでも同じ正午となった。なお、明石市相生町にある子午線標識は、1928年(昭和 3年)に昭和天皇の即位を記念して建造されたもの。
◆ローリング・ストーンズ記念日
1962年(昭和37年)のこの日、ローリング・ストーンズが初めてロンドンのクラブに出演したことを記念。
◆人間ドックの日
1954年(昭和29年)東京の国立第一東京病院で「人間ドック」が始められたことを記念し。
◆洋食器の日
新潟県燕市にある日本金属洋食器工業組合が、代表的な洋食器のナイフ(712)の語呂合わせからこの日を「洋食器の日」と制定。
[この頃、こんな季節]
●鬼灯(ほおずき)
◆夏になると真っ赤な実をつける「ほおずき」。赤い実の中身を抜いて口に入れ、鳴らしたこともあるだろう。
◆ほおづきは、6月頃に淡い黄白色の花をつけ、やがてガクが大きくなり、ちょうど袋をかぶせたように実を包み込んでしまう。ほおずきが店に出てくるのはお盆前くらいから。
◆ほおずきといえば東京・浅草、浅草寺のほおずき市が有名だが、福岡市西区の愛宕神社でもこの頃「ほおずき祭り」が行われる。境内は2000鉢程のほおずきで一杯になり即売会も行われる。
◆ほおずきの見分け方。茎がしっかりとしていて、実の付きがよいものを選ぼう。
◆ほおずきの育て方。日当たりのよい場所で育てよう。表面の土は、常時湿っている程度がいい。
Posted by
うさぎいぬ
at
22:42
│Comments(
0
)
ちちんぷいぷいが…
 TBSやMROなどでは毎週金曜日に放送している毎日放送の「ちちんぷいぷい」が今週末で打ち切りになるようです。
TBSやMROなどでは毎週金曜日に放送している毎日放送の「ちちんぷいぷい」が今週末で打ち切りになるようです。編成上の都合のほかに視聴率の低迷が理由のようですが、私は「ちちんぷいぷい」のまったりとした内容がよかったですけど残念ですね。
Posted by
うさぎいぬ
at
13:12
│Comments(
0
)
ムーンライト九州、静かに引退
ムーンライト九州、事前発表もなく姿消す
7月12日7時51分配信 読売新聞
JR九州と西日本が共同運行していた夜行の臨時快速列車「ムーンライト九州」(博多-新大阪)が10日、廃車処分され、姿を消した。
乗客減で今春の運行が見送られ、鉄道ファンから復活を求める声が出ていたが、かなわなかった。若者を中心に重宝された長距離列車は、臨時列車ゆえに事前に発表されることもなく、静かに引退した。
ムーンライト九州は1990年4月に博多-京都間で運行が始まり、春、夏、冬休みの期間に1日1往復していた。近年は、博多-新大阪間で運行。約620キロの道のりを9時間半から10時間かけて走った。寝台車両はなく、乗客は座席をリクライニングさせて体を休めた。
それでも乗客にとっては魅力的な列車だった。全国のJR線で普通、快速列車で乗り降り自由の「青春18きっぷ」を使えば、指定席料金を含め、5110円で済み、新幹線(自由席)に比べ、6割以上安く乗車できた。特に年末年始や盆には、帰省の若者の姿が目立ったという。
しかし、近年は低料金の高速バスとの競合などで空席が目立ち、運行本数も次第に減少。2003年度に往復で計160本あった本数は、昨年度は半減となる86本にまで落ち込んでいた。
加えて2編成16両ある車両も平均車齢35年と老朽化。今春のダイヤから姿を消し、このほど車両の処分が決まった。車両は順次解体されるという。
九州と本州を結ぶ夜行列車は、JR発足時の1987年には特急のブルートレインだけで8本あった。だが、乗客の減少で次々と運行が終わり、今年3月に寝台特急「はやぶさ」(東京-熊本)、「富士」(東京-大分)の廃止で、特急はすべてなくなっている。ムーンライト九州は、元々、臨時列車扱いだったため、公表はされなかった。
旅行の際に頻繁に利用したという九州鉄道記念館(北九州市門司区)の宇都宮照信館長代理(59)は「乗り合わせた人と盛り上がった旅の話は本当にいい思い出。時代の流れなのだろうが、本当に寂しい」と惜しんでいる。(網本健二郎)
最終更新:7月12日7時51分
青春18きっぷ利用者(18キッパー)の味方であるムーンライト九州が誰にも知らされることなく、ひっそりと引退。車両は廃車処分されたそうです。
ムーンライト九州に使用されていた14系客車は指定席料金の510円を支払えば利用できたため、長距離を移動するときには重宝していたものでしたが、昭和40年代から活躍していた車両で傷みも激しく、車両の塗装が剥げていたり冷暖房の故障があったりしていました。
しかし、高速バスは料金が安いとはいっても列車のほうが自由が利くので、高速バスよりもムーンライト九州を選んでいた人もいると思います。
ちなみにムーンライトながら(東京‐大垣)やムーンライトえちご(新宿‐新潟)は臨時列車ながら特急用電車を使用して運行されています。ムーンライト九州も485系の特急用電車を使用して運行する事は検討できなかったのでしょうか。
鉄道会社が列車がエコな乗り物と謳うのなら、クルマより列車にシフトさせるのがベストだと思うのですが…
7月12日7時51分配信 読売新聞
JR九州と西日本が共同運行していた夜行の臨時快速列車「ムーンライト九州」(博多-新大阪)が10日、廃車処分され、姿を消した。
乗客減で今春の運行が見送られ、鉄道ファンから復活を求める声が出ていたが、かなわなかった。若者を中心に重宝された長距離列車は、臨時列車ゆえに事前に発表されることもなく、静かに引退した。
ムーンライト九州は1990年4月に博多-京都間で運行が始まり、春、夏、冬休みの期間に1日1往復していた。近年は、博多-新大阪間で運行。約620キロの道のりを9時間半から10時間かけて走った。寝台車両はなく、乗客は座席をリクライニングさせて体を休めた。
それでも乗客にとっては魅力的な列車だった。全国のJR線で普通、快速列車で乗り降り自由の「青春18きっぷ」を使えば、指定席料金を含め、5110円で済み、新幹線(自由席)に比べ、6割以上安く乗車できた。特に年末年始や盆には、帰省の若者の姿が目立ったという。
しかし、近年は低料金の高速バスとの競合などで空席が目立ち、運行本数も次第に減少。2003年度に往復で計160本あった本数は、昨年度は半減となる86本にまで落ち込んでいた。
加えて2編成16両ある車両も平均車齢35年と老朽化。今春のダイヤから姿を消し、このほど車両の処分が決まった。車両は順次解体されるという。
九州と本州を結ぶ夜行列車は、JR発足時の1987年には特急のブルートレインだけで8本あった。だが、乗客の減少で次々と運行が終わり、今年3月に寝台特急「はやぶさ」(東京-熊本)、「富士」(東京-大分)の廃止で、特急はすべてなくなっている。ムーンライト九州は、元々、臨時列車扱いだったため、公表はされなかった。
旅行の際に頻繁に利用したという九州鉄道記念館(北九州市門司区)の宇都宮照信館長代理(59)は「乗り合わせた人と盛り上がった旅の話は本当にいい思い出。時代の流れなのだろうが、本当に寂しい」と惜しんでいる。(網本健二郎)
最終更新:7月12日7時51分
青春18きっぷ利用者(18キッパー)の味方であるムーンライト九州が誰にも知らされることなく、ひっそりと引退。車両は廃車処分されたそうです。
ムーンライト九州に使用されていた14系客車は指定席料金の510円を支払えば利用できたため、長距離を移動するときには重宝していたものでしたが、昭和40年代から活躍していた車両で傷みも激しく、車両の塗装が剥げていたり冷暖房の故障があったりしていました。
しかし、高速バスは料金が安いとはいっても列車のほうが自由が利くので、高速バスよりもムーンライト九州を選んでいた人もいると思います。
ちなみにムーンライトながら(東京‐大垣)やムーンライトえちご(新宿‐新潟)は臨時列車ながら特急用電車を使用して運行されています。ムーンライト九州も485系の特急用電車を使用して運行する事は検討できなかったのでしょうか。
鉄道会社が列車がエコな乗り物と謳うのなら、クルマより列車にシフトさせるのがベストだと思うのですが…
Posted by
うさぎいぬ
at
11:45
│Comments(
0
)