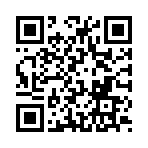今日の出来事…9月20日(お手玉の日)
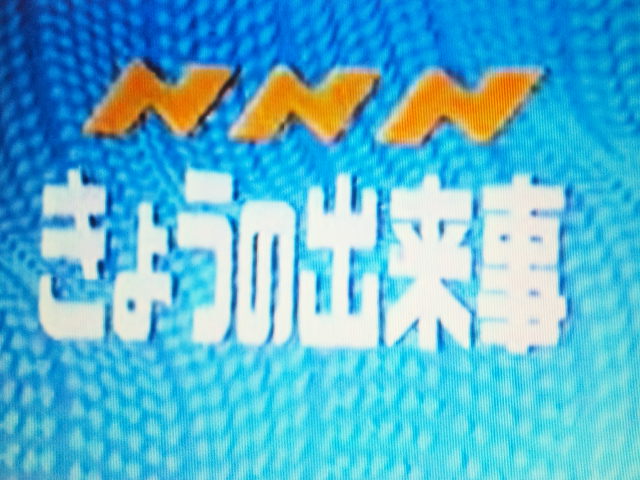
[今日が誕生日]
●末吉興一(前北九州市長・1934年生)
●ソフィア・ローレン(女優《ひまわり》・1934年生)
●麻生太郎(政治家・前内閣総理大臣・1940年生)
●村井国夫(俳優・1944年生)
●小田和正(ミュージシャン・1947年生)
●五十嵐淳子(女優・1952年生)
●石川ひとみ(歌手《まちぶせ》・1959年生)
●鈴木砂羽(女優・1972年生)
●丸山茂宏(ミュージシャン《オセロケッツ》・1973年生)
●新藤晴一(ミュージシャン《ポルノグラフィティ》・1974年)
●一青窈(ミュージシャン・1976年生)
●安室奈美恵(ミュージシャン・1977年生)
●若林正恭(お笑い芸人《オードリー》・1978年生)
●杏さゆり(タレント・1983年生)
●伊藤由奈(ミュージシャン・1983年生)
[今日が命日]
●ヤーコプ・グリム(文学者《グリム兄弟の兄》・1863年没・78歳)
●鈴木梅太郎(化学者《オリザニン=ビタミンB1の発見者》・1943年没・69歳)
●ジャン・シベリウス(フィンランド作曲家・1957年没・91歳)
●林家三平(落語家《ネタ:よし子さん・どうもすいません》・1980年没・54歳)
●中村汀女(俳人・1988年没・88歳)
●白石一郎(直木賞作家《海狼伝》・2004年没・72歳)
[今日の歴史]
●1519年(永正16年)
スペインのサン・ルーカル・デ・パラメダ港から、マゼランが世界一周航海に出発。旗艦(きかん)のトリニダード号、サン・アントニオ号、コンセプシオン号、ビクトリア号、サンティアゴ号の計5隻の船団で乗組員260余名を乗せて出航した。
●1868年(明治 元年)
明治天皇が、京都を出発し、東京に。
●1886年(明治19年)
大阪の紡績会社が、夜間作業のため、民間企業として初の電灯を使用。
●1925年(大正14年)
東京六大学野球のリーグ戦が始まる。この日、明治VS立教戦が連盟創設初試合として行われた。
●1946年(昭和21年)
戦後初の国際映画祭である「第一回カンヌ映画祭」が開催された。
●1948年(昭和23年)
花森安治氏らにより「暮しの手帖」が創刊。創刊当時は「美しい暮しの手帖」。花森氏は、暮しの合理化を目指す雑誌づくりに取り組み、独自の商品テストなどで読者の信頼を得た。
●1957年(昭和32年)
糸川英夫東大教授らにより国産初の観測用ロケット「カッパー4C型」1号機の打上に成功。秋田県岩城町にある東京大学生産技術研究所秋田ロケット実験場で行われ、高度約4万5000mに到達したとき、搭載したガイガーカウンターで宇宙線を観測。ロケットは全長5.93m、重量378kだった。
●1962年(昭和37年)
国内初の国際レーシングコースとなる「鈴鹿サーキット」が完成。
●1987年(昭和62年)
"セーラー服を脱がさないで"などがヒットした「おニャン子クラブ」が解散。
●1994年(平成 6年)
オリックスのイチロー選手が対ロッテ戦で、前人未到の1シーズン200本安打を記録。このシーズン、最終的にイチロー選手は、210安打、69試合連続出塁の大記録を樹立。
[今日の暦と記念日]
◆彼岸入り
秋の彼岸の始まりの日。先祖への感謝と供養を行い、墓へ参る。暑さ寒さも彼岸までのたとえどおり、暑さも終わりに。
◆空の日
国土交通省航空局によると、「空の日」は、1940年(昭和15年)に制定された「航空日」が始まり。この年は、日野・徳川両陸軍大尉が代々木練兵場にて日本で最初の動力飛行を披露した1910年(明治43年)からちょうど30周年に当たることなどから、政府は、航空の歴史を記念し将来の発展に努めるため、1940年6月13日の各省次官会議において「航空日」の制定を決定。この年の「航空日」は9月28日に行われたが、翌年の1941年(昭和16年)、航空関係省庁間協議で9月20日と決定。第2次大戦終戦に伴う一時休止もあったが、1953年(昭和28年)に再開され、民間航空再開40周年にあたる1992年(平成4年)に、親しみやすいネーミングということで、「空の日」と改称された。また、9月20日〜30日までの「空の旬間」も設けられた。
◆バスの日
1903年(明治36年)の今日、日本で初めてバス会社が本格的な営業を開始した事に由来する。京都の堀川中立売(ほりかわなかだちうり)〜七条(しちじょう)〜祇園の間を走ったこのバスは、蒸気自動車を改造したもので幌のない6人乗り。「バスの日」は、1987年(昭和62年)の全国バス事業者大会で制定された。
◆お手玉の日
日本お手玉の会が制定。1992年(平成4年)に第1回全国お手玉遊び大会が愛媛県新居浜市で開かれた。お手玉は、紀元前に、今のトルコにあったリディア王国というところで誕生。これが、ギリシャに伝わり、古代ギリシャでは「アストラガリ」という呼び名で、羊の骨を使って遊んでいた。この「アストラガリ」が、シルクロードを通って、インドや中国に伝わり、インドでは、骨に変わって、ナツメヤシの実が使われ、奈良時代に日本に伝わったときには、小石に変わり、「石なご」と呼ばれていた。
◆動物愛護週間
国民の間に広く動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めてもらうため、動物愛護管理法で、9月20日から26日を動物愛護週間と定めている。
[この頃、こんな季節]
●アカトンボが里に舞うころ
◆アカトンボが里に下りてくる頃。稲刈りが終わった田に、2匹仲良く並んで飛んでいる様子を見かける。
◆日本で知られているアカトンボは「アキアカネ」で6月頃に羽化し、山地へといく。夏の間を山で過ごしたあと、9月下旬から10月にかけて里に下りてくる。ひと夏を山で過ごす理由は判明していないが、アキアカネの場合、気温が20度から25度の場所が棲むには最適の地のようで、十分に休養を取るために平地より涼しい山で過ごしているのでは・・・・という説がある。そして、体を赤色に変え、大人になって平地へと下りてくる。
Posted by
うさぎいぬ
at
18:00
│Comments(
0
)